いわゆる毒親と言われる親の元で育つと、幼少期や小学生から辛い日々を少しずつ重ね、何が辛いのかもわからないまま成長して来た子供。
いつの間にか中学生という思春期の入るような年頃になってもその影響は続き、本来あるはずの思春期も他の友達のようには感じられず、そういう感情のない日々を過ごす事になったりします。
その辛い日々は、大人にまた一歩近づいた年齢では他の要素と相まって劣等感という現実を突きつけられ、大人になる前から生き辛さが心を襲う事になります。
この記事では、中学生の頃に劣等感を感じてしまい、それが心を壊していく現実について述べてみたいと思います。
※この記事にはアフィリエイト広告が含まれています。
傷付いている事を確信する時期
小学生でも人によっては親に対する不信感や自分の家庭が他と違う事を感じ取るようになるのに、中学生ともなればその事実に確信を持つようになります。
それだけ大人に一歩近づき、大人の世界が徐々にはっきりして来る頃なのです。
小学生ではまだそこまでわからなくても、中学生では友達と比べたり自分の心の中がおかしいなと何となくわかって来ます。
そして自分だけが違うと思うと、劣等感が生まれたり、家庭への不信感が更に増して行く事になったりし、辛ささえ感じないほど心が壊れたりします。
勉強が出来ない劣等感
家庭内が不安定だと落ち着いて日常生活を送る事ができず、勉強にも集中出来ない状態になったりします。
特に暴力的な親と一緒では恐怖心から勉強に集中出来なくなって、それで成績が悪いと更に叱責されるという悪循環に陥って、安心できる場がなくなります。
学校の成績が悪いと、どうせこんなもんだと思ってはみても、心の中は幼少期から比較する事が癖になっているため、自分が夢見ていた成績の良い学生とのギャップで劣等感が蓄積されて行くのです。
家庭状況を比較した劣等感
小学生くらいまではまだ自分の家庭が他の家庭と違う事がはっきりわからなかったり、劣等感もそんなには感じなくても、中学生となれば段々とはっきりして来ます。
もう大人への階段は個人差はあってもかなり昇っていると思います。
最後の義務教育3年間で、友達関係も変って来たりしますが、自分の家庭の状況が影響する場合もあります。
新しい友達が出来ても自分の家の話をする事に抵抗を感じ、他と比べて人に言えるような家ではないんだという事がわかっているので、心の中で劣等感を感じてしまうのです。
先生に感じる親の影
中学生になると小学生の時のように一人の先生が殆どの事を教えるという事から変わり、教科によって先生が変わるというスタイルになって来ます。
その先生も色々な性格があり、好きな先生や嫌いな先生がいる事も当たり前でした。
中には大好きな先生がいたり、逆に大嫌いな先生がいて、感情が揺れ動くという事になります。
大嫌いな先生も色々なタイプがありますが、中には親と同じようなタイプもいます。
親が怒鳴ってばかりだと、怒鳴ってばかりいるような先生が現れたり、親が暴力的だと暴力的な先生が現れたり。
今の時代では暴力的な先生は大問題になりますが、そういう時代に生きて来た人は、暴力的な先生が当たり前にいた事も記憶の中にあると思います。
親を投影する人生へ
そのように親と同じタイプの人間に出会う事を投影といいますが、子供の頃はそれを知る由もなく、ただ嫌な思いばかりに心が囚われてしまいます。
それは大人になっても続く訳ですが、学生時代ではそんな事を思いもせずに、この状況から解放されるなら早く大人になりたいと、大人への希望を考えてしまいます。
それは先生に限らず、友達であったり、たまたま出会った大人であったり、色々な所で親が投影された人に出会ってしまい、その度に嫌な思いをし傷付くのです。
運の悪さが劣等感を構築
本来、人生は運だけで決められるものではありませんが、中学生くらいでは嫌な事に遭遇すると運が悪かったと思うのも当然だと思います。
そうした運の悪さが蓄積されると、何で自分ばかりこうなるんだと落ち込み、人によっては劣等感に追い打ちをかけるようになり、辛さもマヒしたりします。
逆に反骨心から不良グループなどに入り荒れた時間を過ごす事で自分を保とうとする者もいて、真逆な道をそれぞれが進んでしまいます。
そうした反骨心が生まれる状況に陥った者にとっても運が悪いという意識が芽生えているという事になります。
いずれにしてもその年代では大人の世界にまだ足を踏み入れてもいないので、運が悪いという事を自分に言い聞かせて、周りを羨んだりしながら生きている事が多いのです。
まとめ
中学生になると小学生の時とは違う世界を感じるようになり、それまで気付かなかった劣等感を感じたり、惨めな思いをして、思春期に心が壊れてしまう事もあります。
場合によっては何が辛いのかさえ分からなくなるほど心の傷は大きい事もあります。
多くの傷付いた同じ年頃の人が、よその家庭が良く見えたり、自分の家が普通ではない事に確信を持ったりして、心が大きく揺れ動く年代となって来たのです。
他の家が良く見えても、その家庭内の事がわかるはずもなく、自分の家よりひどいかも知れないという事を考える余裕はなく、ただ比べてしまい、それがまた劣等感を大きく感じる事になるのです。
思春期という多感な時期に、家庭内の事などの余計な刺激が心を不安定にし、人によってはその心が壊れてしまう事に繋がって行くのです。
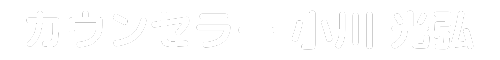

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/43dce4b4.69354431.43dce4b5.83c4154f/?me_id=1285657&item_id=13034605&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01158%2Fbk4569905072.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

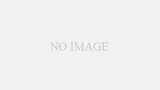


コメント